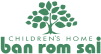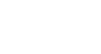写真日記
床屋の奥さん
半月ほど前、2カ月に1回私の髪を刈ってくれる、近くの床屋の奥さんが亡くなりました。
ホームから2分ほどのハンドン市場に向かう細い道路に面した、いつも開けっぱなしの門を入った家の5、6段ほど上った二階のテラスの青いプラスチックの椅子に座った奥さんは、日がな一日外を眺めていました。
初めて行った時、普通の民家なのでどこが床屋、、、、と事情が分からず、下からその奥さんに声をかけたのですが返事はなし、、、、その後いつ行ってもその奥さんはテラスに座り、少し顔をしかめて黙って座っていました。その奥さんが家で食後ティシュを食べ、喉に詰まらせ亡くなってしまったのです。
チェンマイからハンドンに向かう大通りをいつも一人でブツブツ言いながら小走りに歩いている細くて小さなおばさんがいます。よく行くクッティオ屋さんの前でも何回か彼女を見かけました。お店の人がお菓子を上げていました。
月に2,3回はお世話になっている市内の動物病院の前の、交通量の多い大通りでは裸足の若い男の人の姿を度々目にします。いつも歩道と車道の丁度境を何も持たずにある時は下り車線を、ある時は上り車線をただただ俯いて歩いています。
52歳の床屋の奥さんがいつから精神に異常をきたしたのかは分かりませんが、住み慣れた家に家族とともに最後まで暮らせたのは、彼女にとって幸せだったと思います。旦那さんはテラスの下の小さな部屋でお客さんの髪を刈っている。人の出入りも多く、声をかけてくれる人もいたでしょう。成人した息子も一緒に住んでいる様子でした。そんな環境の中、床屋の奥さんは毎日小奇麗な庭と外を通る人を静かに眺めて過ごしていたのです。
一昔前、私が子どもの頃、家の近くに「きちがいおじさん」と呼ばれていた男の人がいました。いつも浴衣をだらしなく着てふらふらとしているだけ、声を荒げる事もなく、ただふらふらと歩いているだけ。毎年夏休みを過ごした国府津の家の近くにも、「ちょっとばか」な男の人がいましたし、一時住んでいた葉山の町にも「おもらいおばさん」と言うおかしなおばさんがいました。
それがどこか当たり前の風景で、子どもたちも「そういうもの」と自然に受け入れていたように思います。おもしろげに見る事や時々彼らの事を話題にしたとは思いますが、意地悪をしたり差別することはありませんでした。
今の日本にも沢山「ちょっとおかしなひとたち」がいます。その人たちの多くは「知的障害者」「精神障害者」とレッテルを張られ施設や病院に収容されているか、なるべく人の目に触れないような暮らしをしているのでしょう。「障害者」と呼ばれどこかに隔離され生きるのが良いのか、、、「きちがいおじさん」とか呼ばれながらも地域の一人として生きるのが良いのか、、、
(この呼び方は決して差別用語としてだけ使われていたのではなく、どこか暖かい意味合いもあったように思います。と言うか人々が丁寧に生きていたからなのか、余裕をもって暮らしていたからなのか、人間たちが今よりずっと「あたたかかった」記憶があります)
彼らは今では身近な存在ではなく、あるスペースに収容された特別な存在になってしまいました。私たちの目に触れず、普通に付き合う事も出来なくなり、付き合い方や共生する仕方を忘れ「そういうもの」として自然に受け入れることもなくなりました。
床屋の奥さんが亡くなって旦那さんはきっと少しはホッとした気持ちもあるでしょう、でも毎日あそこにいた奥さんがいないと言う事実は、きっととってもさみしいものでしょう、、、、、
名取 美和|2009/08/31 (月)
前の写真日記:ガノック
次の写真日記:残業